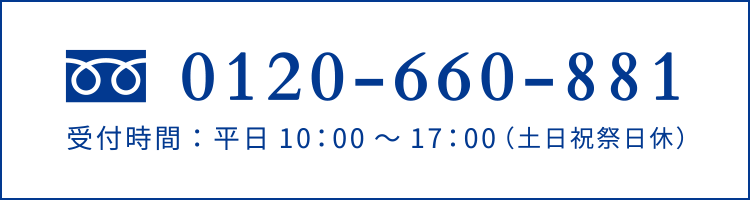

男性の育休取得40% 前年度から大幅上昇
厚生労働省がまとめた令和6年度「雇用均等基本調査」の結果によると、男性の育児休業(育休)取得率が初めて4割を超えたことが明らかになりました。令和4年10月1日から5年9月30日までの1年間に子どもが生まれた男性労働者を対象に、6年10月1日までに育休を開始した割合を調べたもので、その取得率は40.5%に達しています。これは、前年度の30.1%から10ポイント以上の大幅上昇となり、調査開始以来の過去最高を記録しました。
注目すべきは、産後パパ育休(出生時育児休業)の利用状況です。育休を取得した男性のうち、出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度を活用した人の割合は60.6%に達しました。2022年の法改正により制度が導入されて以降、認知度や利用率が徐々に高まってきたことが数字に表れているといえます。
また、雇用形態別に見ると、有期契約で働く男性の育休取得率も改善がみられました。33.2%と、前年度の26.9%から6.3ポイント上昇しており、非正規雇用の男性にも育休取得が広がりつつあります。ただし、依然として正社員に比べれば取得率は低く、今後の課題も残されています。
業種別にみると、その差は一層鮮明です。鉱業・採石業・砂利採取業で67.7%、金融業・保険業で63.6%、学術研究・専門・技術サービス業で60.7%と、6割を超える業種がある一方、生活関連サービス・娯楽業は15.8%、不動産業・物品賃貸業は19.9%と、2割未満にとどまっています。業種によって職場環境や人員体制、育休を取りやすい風土に大きな違いがあることが浮き彫りになりました。
政府は「育児休業の取得促進」を重点政策のひとつに掲げており、特に男性の取得率については2025年度に50%、2030年度には85%という目標を定めています。今回の調査結果は、その達成に向けて大きな一歩となるものの、依然として業種や雇用形態による格差が大きく、制度を実際に利用しやすい環境整備が不可欠です。
男性の育休取得は、子育て期の家族を支えるだけでなく、社会全体の働き方や企業文化を少しずつ変えていく力を持っています。ただし、今回の取得率の上昇をもってもう十分と考えるのは早計です。いまだ多くの職場では、長時間労働や人手不足、そして「育児は女性が担うもの」といった意識が残っており、育休取得に踏み切れない男性も少なくありません。
育休は、単なる個人の選択ではなく、社会の持続可能性に関わる重要なテーマです。今回の数字は着実な前進を示す一方で、より多くの人が安心して育休を選べる環境づくりを社会全体で進めていくことが求められています。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-
☆ 一般社団法人全国労務監査協会 ☆
★<東 京 本 部> 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 10F
★<大 阪 本 部> 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目2番123号イノゲート大阪 15階
TEL 0120-660-881 FAX 03-3548-0698 06-6136-2960
Email: ss.info@roumukansakyoukai.com URL : http://www.roumukansakyoukai.com/
労務監査ご案内⇒ www.youtube.com/watch?v=VvdNE0CwWQ
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-